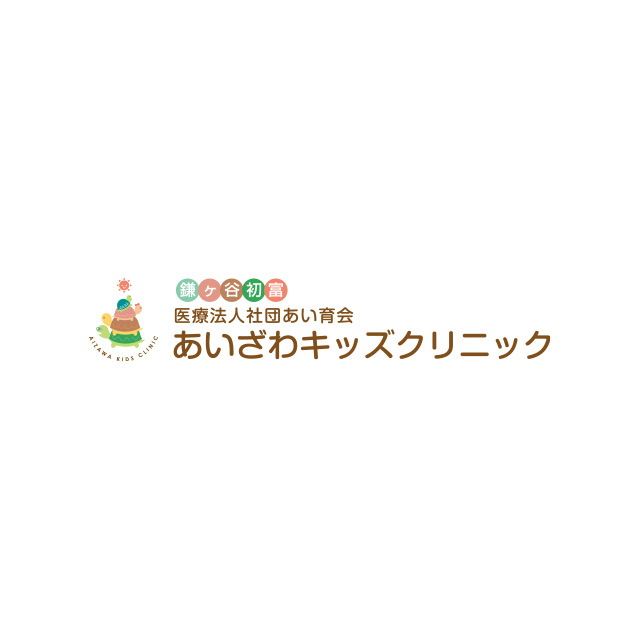最後に、最も重要な予防についてです。
このブログの読者はお子様の保護者が多いはずです。こども(特に小さいお子様)はところ構わず手で触り、またその手を口に持って行ったりします。また、好奇心から動物を触ろうとすることもあるでしょう。他に公園や砂場で遊んだりもします。
いずれも感染のリスクとなります。
更にこれから夏休みに向かい、動物との接触が増えたり、皮膚の露出も増えたりします(経皮感染もあります!)。良くお読みください。
まず飼い主側の予防としては、
①ペット(パートナーアニマル)の予防接種、登録。
②過剰なふれあいは控える。口移しの食事や同じ布団で寝る等。
③ペット(パートナーアニマル)周辺の清潔保持。
④糞尿の速やかな処理。糞尿が乾燥するとその中の病原体が空気中を漂い、人間が吸い込んだり触れたりしやすくなる。
⑤室内で鳥を飼育する場合は換気を心掛ける。羽毛や排泄物が室内に充満する。
次に飼い主以外の方も含めての予防です。
以下を心掛けてください。
①動物に触ったら必ず手洗いをする。
動物には無害でも人間には有害な病原体もあります。動物の毛に菌や病原体の卵が付着していることもあります。気付かずに動物の唾液や粘液に触れてしまうこともあります。
②病気の動物や弱った動物の周辺には近づかない。
動物を心配したりして近づこうとするのでしょうが、当然感染のリスクは上がります。どの様な病原体で弱っているのか、あるいは周囲に巻き散らしているのか、不明です。
③野生動物を触ったり飼育したりしない。
どんな病原体を保持しているか不明です。
④公園や砂場で遊んだら手洗いをする。
公園や砂場は動物が排泄を行いがちな場所です。
⑤動物園や水族館の展示動物は、施設で比較的健康管理に注意されていることや人間との直接接触が限定的であることなどから動物由来感染症の感染源になることは少ないと考えられています。しかし集団発生の事例もあります。やはり手洗い等の予防や注意は必要でしょう。
動物と接することは楽しいし情操教育にも役立ちますが、感染のことも頭の片隅に入れて接して戴き、手洗いを励行して戴けたらと思います。
パートナーアニマルの場合はご家族のお考えに任せますが、それ以外の病気の動物や弱った動物、その周辺に近づくことは特にお控えください。お子様が予想外の感染症にかからない様に気を付けましょう。